スポーツ上達
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
ソフトボールピッチャー ピッチング強化トータルグッズセット
ピッチングは最後のリリース時にビシッと決める!!これが何よりも上達の要です。
では、ビシッと決めるとは一何でしょうか?
それは、指先とリリース時の手首の感覚です。
残念なことに、この感覚は教えようと思っても教えることができないので
選手本人につかんでもらうしか他はありません。
だからこそ、多くの球を投げて感覚をつかむ練習をするという流れに走りがちですが
ソフ研は、その危険な練習法には警笛を鳴らしたいと思います。
そこでご紹介したいのが、最新のピッチング強化グッズを使ったピッチング練習法です。
一球一球投げるごとにピッチング上達に欠かせない指先とリリースの感覚を養い
スピードアップと、変化球への磨きをかける練習法です。
子どもたちの肩に負担をかけずに、ピッチングを最短距離で上達するための練習法を実現するために日頃から元気ソフトボールスクールのトレーナーとして絶大な信頼を寄せている高夕子さんに指導をお願いしました。
>>> ソフトボールピッチャー ピッチング強化トータルグッズセット
PR -
左・右投手の特徴を徹底比較DVD 【ソフトボール ピッチャー】
右投手では、今までなんとなく曖昧だったブラッシングや身体の使い方が明確になります。
右投手のファーストボール、変化球、それぞれのブラッシングの位置とリリースがよくわかります。
重心の位置、腕の回転、リリースの仕方など全てにおいて右投手と左投手の違いが明確になります。
バッターの目線でも撮影しているので、バッターにはどう見えているのかがわかります。
変化球が思うように投げられなかった人には理由がはっきりします。
なぜ、今まで左投手を教えていてもスピードが上がらなかったのか? この疑問が解決できます。
軸足へ乗りやすくするための簡単な方法とは?
力強いボールを投げるための右半身の使い方とは?
速いボールを投げるための肘と前腕の使い方とは?
左投手に有効な膝の使い方とは?
左特有のカーブ系のボールを投げるときの前腕の使い方とイメージの仕方とは?
セット時からのグラブの使い方とは?
早くなりすぎるリリースの修正法とは?
自分の体をコントロールするためにどこに意識をしたらよいか?
ボールの軌道のイメージの仕方とは?
左投手の体重移動と腰の使い方とは?
ステップがクロスに入りすぎるのを修正するには?
できるだけ肩を動かさずに、どこを支点としてリリースしていくのか?
できるだけ肩を動かさずに、どこを支点としてリリースしていくのか?
左投手はどこのコースに確実に投げ込むことが重要か? どこのコースの出し入れが重要か?
キャッチャーだけを見るのではなく、何を見ることが大事なのか?
左投手特有のカーブドロップを投げるためのポイントとは?
カーブドロップにさらに回転をかけるための握り方とは?
左のライズボールを投げるための握りとコツとは?
一番重要なのは、左投手と右投手への指導は違うということを理解していただくこと。
そして、指導者として左投手も右投手もそれぞれの特長を生かしながら伸びてほしいという気持ちです。
今回は、左投手・右投手の特長を比較しながら指導法を解説しています。
選手が見ても分かりやすいようにしてありますので、投手経験のない方もその内容を必ず理解していただけます。
>>>> 左・右投手の特徴を徹底比較DVD 【ソフトボール ピッチャー】
-
川﨑宗則監修 実践守備マスタープロジェクト
エラーばかりの初心者が、たった21日でチーム一の遊撃手に変わった秘密!
守備の『基本』から『応用』、『練習メニュー』まで、お子さんへの守備上達の秘訣のすべてを公開します。
コレで守備の名手になれる!メジャーでも絶賛される川崎選手の超一流の “グラブさばきの秘密”を初公開!
このグラブさばきの秘密を知れば、難しいゴロでも難なく捕球できるようになり、エラーをグンと減らせるでしょう。
なぜ、試合前にこの『ムネリン流キャッチボール』をするだけで、悪送球の確率がグンと下がるのか?
80%以上の野球選手が意識していない、〇〇を意識するだけのムネリン流キャッチボール。しかし、この〇〇を意識して毎日キャッチボールをするだけで、送球の精度が大幅に向上します! その秘密は、、、
【注目】守備時の構えに ”ある要素” を付け足すだけで、お子さんの守備範囲が大きく広がることをご存知でしたか?
ここでは、プロ野球選手も実践している、守備範囲が広がるようになる”ある構え方”を、セカンド、ショート、サードそれぞれのポジション別に公開します。
難しい打球でも、正面で正確に捕球できるようになる“守備時の動きの秘訣”とは?
これをご覧になれば、俊敏性と判断力が上がり、難しいボールでも身体の正面でしっかりと捕球できるようになるので、エラーの確率がガクッと落ちます。
なぜ、この練習法を1週間試しただけで、トンネルばかりしていた選手が一切エラーをしなくなったのか?
強豪チームやプロでも実践されるある練習法について公開します。「目を瞑ってしまう」ような守備のミスに悩まされているのなら必見です。
【警告】「腰を落とせ!」と指導しているチームが決して強くなれない致命的な理由…
もし、あなたのお子さんのチームでこのような指導をされているのならば、絶対にコレは見逃さないでください。お子さんの守備力の低下に繋がります。
小学校低学年の子でもできた!“ビビり”の内野手でも強い打球に全く怯えなくなり、正確に捕球できるようになった”捕球技術”を公開!
特にサードの子は必見です。この方法を知れば、今よりも捕球技術が上がります。
川崎宗則が明かす、『正確な送球』をするために知っておくべき“ある動作”とは?
この動作はとてもシンプルです。しかし川崎選手は送球時に、何よりもコレを重視しています。そして、あなたやお子さんがこれをマスターすれば、正確に、素早くファーストに送球でき、今よりもランナーをアウトにできる確率を高めることができます。
守備範囲が格段に広がる “メジャー式” 逆シングルを完全解説!
この逆シングルを知れば、今まで追いつけなかった難しい球でも捕球できるようになり、プロからも守備力を注目される名選手になれるでしょう!
【注意】もしあなたのお子さんが” あるクセ”をもっていたら、成長するにつれて内野手として活躍できなくなっていくでしょう
ここでは、その致命的なクセとその解決法を公開します。お子さんのためにも、ぜひご覧になってください。
【指導者さん必見】川崎宗則が語る、守備の指導時に『絶対にやってほしくない』間違ったアドバイスとは?
ほとんどの指導者さんが思わず言ってしまうことなのですが、実はコレ、『完全な間違い』なんです…。ここでは、野球少年の上達のチャンスを潰してしまいかねない『間違ったアドバイス』の内容と、それを防ぐ方法を解説します。
【全選手必見】フライ捕球時に、ボールから目を切ることなく落下地点まで一直線に移動できるようになる”川崎流?テクニック
『どんなにレベルの高いチームでも活躍できる内野手』が実践している”一塁手が取りやすい送球”とは?
実は一塁手には、[捕りやすい球]と[捕りにくい球]があります。そして、ここでお話しする[取りやすい球]とその投げ方を知れば、どのようなチームでもチームメイトやコーチ達に信頼され、『守備のスペシャリスト』として試合に出場するチャンスを増やせるでしょう。
【肩が弱いお子さん必見】弱肩だった子が、わずか29日で矢のような送球ができるようになった秘密の練習法とは?
チームの内野陣をワンランク上に引き上げる“超実践的守備練習”の全貌を公開
体格で劣る川崎選手が、メジャーの俊足ランナー相手でもアウトを量産できる秘密でもある “捕球スピードを上げる方法” を公開。
川崎選手は決して強肩ではありません。しかし、これまで大リーグ・プロ野球の舞台で『あること』を実践してきたからこそ、どんなに足の速い選手が相手でも、素早いスローイングによってアウトを量産することができたのです。ここでは、その秘密を公開します。
現役プロも絶賛!難しいゴロの捕球時でも”お手玉”をしなくなる “グラビングテクニック”
これをご覧になれば、他の内野手よりかなり守備面でリードでき、『守備の名手』としてチームでの絶対的な地位を確立できるでしょう。
悪送球が来てもしっかり捕球・アウトがとれる“タッチプレーでのテクニック”
タッチプレーでアウトを取る確率を高める秘密は”このベースの使い方”にあります。これをマスターすれば、たとえ悪送球がきても、素早く対応できるのでしっかりアウトが獲れます。

この『3つのアドバイス』を聞けば、素早く的確なカットプレーができるようになります!
内野手として絶対に知っておくべき技術なので、中継プレーの精度を上げたいならば必見です!
ほとんどの日本人指導者が知らない『メジャー流ランニングスロー』のやり方を完全解説
ボールを取ってから素早く送球する方法が知りたい方は必見です。華麗でなおかつ実用的なスーパープレーのやり方を徹底解説します。
【指導者様必見】ゲッツーを素早く・高確率で取るための、川崎式『6-4-3』『4-6-3』強化練習
併殺プレーが上手な二遊間と、そうでない二遊間の“ある致命的な差“ とは?
併殺プレーを完成させるには、”あることが出来ているかどうか”がとても重要なのですが、実はコレ、意外と知られていません。ここではその “あること” と、ダブルプレー時のポイントを解説します。
川崎選手が、現在も欠かさず行っている“守備力を上げる秘密の練習メニュー”を初公開!
日本時代、アメリカ時代を通して「これは本当に効果があった!」と川崎選手が自信をもってお勧めする『守備力上達のための練習メニュー』を公開します。これでお子さんを守備の名手に育てて下さい!
【三塁手には特におすすめ!】打球方向を一瞬で判断できるようになる練習法を完全公開。
この練習法を実践すれば、お子さんの判断力を大幅に伸ばすことができます。速い打球が飛んできても、素早く反応し、アウトを取れるようになるでしょう。
これぞ“匠の技”!ショートバウンドが簡単に捕れるグラブの使い方の秘密とは?
【新発見】ノックよりも効果的な、捕球技術を高める“ある練習法”とは?
川崎選手が語る、捕球技術を高めるために最適な練習法をご紹介しています。お子さんが打球を怖がっていたりエラーしがちならば、まさにうってつけの練習法です。
あの強豪チームも取り入れている、素早く正確に送球する技術を磨くための”投げ分け練習法”
強豪チームも取り入れて成果を出しているこの練習法を知って、お子さんを鉄壁の内野手に育成してください。
【※本気でプロを目指している方だけご覧ください】接触プレーの際に、自分の体を守りながらもランナーをアウトにする実践的テクニックを公開!
レベルの高い世界では、ベース周りでのクロスプレーも多くなり、怪我のリスクが増えてきます。ここでは、そのリスクを回避し、大切な体を守りながらもランナーをアウトにするための『上級者向けの体の使い方』を伝授します。
メジャーリーガー達が試合前に実践している、守備能力を向上させる”ボール遊び”とは?
なぜ、試合のアップ前にできるこのボール遊びで守備力が上がるのか?
その秘密と方法を公開します。
なぜ、この”お尻”を使った『ユニークな練習法』を取り入れると、送球ミスが大幅に改善するのか?
など、守備の名手にして現役のメジャーリーガーである川崎選手が“守備が上達する”『守備技術』と『守備練習法』を1時間33分にわたって公開しています!
>>> 川﨑宗則監修 実践守備マスタープロジェクト
-
ハンドボール・サイドシュート上達革命【元・日本代表サイドプレイヤー下川監督 指導】
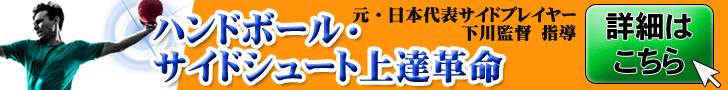
フリーなら絶対止められない、自分の武器となるシュート習得法とは?
実戦をイメージしたシュート練習で、決定率が高いものを極めていきましょう。確実に決められるシュートを持っていると自信につながりますよね。高低差、スライド、フェイント、バックシュート、切り返しなどさまざまなシュートパターンで数をこなし、自分の武器となるシュートを習得しましょう。また、確率が低いシュートも、このプログラムを見てコツをつかみ、強化していくことをオススメします。
シュートにつながる有効なパスを出す秘訣とは?
シュートにつながるパスは、シューターが打ちやすいボールを出すということです。素早いリリースで○の○を狙い、しっかり回転を掛けることが重要です。またパスを出した後の動き方にもコツがあります。この3点を同時に効率よく向上させるトレーニング法を紹介します。
得点チャンスを劇的にアップするシュートフェイント習得方法?
ゴールを意識した、3人一組のパス練習をご紹介します。降りたらすぐに切り返す、そしてシュートをしっかり意識することが大切になりますが、この点について詳しく実演を交えて解説します。このプログラムを繰り返し見て理解し、練習することで試合でも効果的に活用できるようになるでしょう。
チャンスをつぶされる、ラテラルパスのカットを防ぐコツとは?
DFの動きを日ごろの練習で意識していくことが不可欠です。そのうえで、DFを揺さぶり、パスをカットされにくくするコツと、それを無意識に行えるようにするための3人で行う練習法をお教えします。ラテラルパスをカットされるのは、相手に動きを読まれているからです。DFの動きをよく観察し、駆け引きに勝つ為の方法がプログラムには詰まっています。カットされるリスクを減らす3人一組練習法です。
サイドプレイヤー特有のシュートコースで活かせるスピン習得方法とは?
サイドプレイヤーにとっては逆スピンの使い方をマスターする必要があります。サイドシュートは角度がないため、コースは限定され、ラインクロスにも注意しなければなりません。GKの動きをいかに見て対応するか?非常に学びの多い練習方法です。
連係とフェイントを一挙に習得する効率的なトレーニング法とは?
日々の限られた練習時間において、その質を上げるということは重要なことだと思います。3ポイントパスと呼ばれる練習法では、先ほどの、ラテラルパスを実践しながら、センターの選手がシュートフェイントを行いリターンパスをします。その時にDFを立たせるとより実戦に近い形で取り組めるため、効果が上がるでしょう。プログラムを見て、チームワークと個人技術を上げていきましょう。
相手を翻弄するパスワークを効果的に上達させるトレーニングとは?
45度の選手2名とセンターの選手の計3名で行う実践型のトレーニング法があります。センターの選手が非常に重要で、シュートフェイントのかけ方、バックステップでパスをもらわないなど、ポイントがいくつかあります。DFにカットされないパスワークを手に入れるためにうってつけの特訓法をプログラムで紹介します。
実戦の試合で活きる!5人の連動性向上トレーニング法とは?
45度とセンターの3ポイントで、基本的なパス技術を習得出来たら、次は本格的に5人の連動性を上げるトレーニングを紹介します。45度はワイドのポジションを意識しながら、センターを中心DFを揺さぶっていきます。このトレーニングを行う上で注意すべき点について、プログラムでは詳説していきます。
シュートと歩数がどうしても合わない初心者が怠っていることとは?
初心者の方で、シュートまでの歩数が合わない、シュートモーションで最大限の筋力を使えない選手が見られます。そんな選手にお勧めのパス&ゴー練習があるので紹介します。この練習方法をプログラムを見て実践することでシュートの苦手意識を払しょくできるでしょう。
DFをずらしてシュートを打つ!歩幅の改善法とは?
シュートの決定率を左右するのは、シュートリリースもさることながら、DFを翻弄するシュートモーションに入る前の動作です。これを上達させるには、実戦形式でDF、GKを立たせて行うサイドからのカットインをしてシュートするトレーニングが効果的です。3歩をうまく利用し、歩幅の大小、また切り替えしといったテクニックをプログラムを見て磨いていきましょう。
シュートがうまい選手のステップ技術を体得できる練習法とは?
3歩移動を最大限に生かしたステップのパターンをいくつか紹介します。DFとの駆け引きで勝ち、シュート決定率を上げる為に必要な技術です。大きい歩幅でニアに放つ。大きく行くと見せかけて切り返して逆側に投げ入れるといった、相手のポジションに応じて打ち分けることができるようになるでしょう。プログラムを参考に練習し、チームで一番のポイントゲッターになりましょう。

DFの動きを見極め、シュートを決めるスライドの極意とは?
DFのポジションや間合いを見極める極意をあなたに伝授します。シュートの決定率を上げるためには、シュート自体の練習もさることながら、前段階のステップ、つまり歩幅とフェイントを磨くことが重要です。この方法も重ねて解説します。プログラムを見て、チームのエースになりましょう!
フリーでもらう!一歩でシュートを打つためのステップ習得法とは?
ある程度のレベルになると、3歩使うとディフェンスに準備をされてしまうケースが出てきます。そんな時に新たな武器になるのが、パスをもらう前にシュートコースを作っておく方法です。45度の角度で、できるだけ外側にDFをずらしておき、パスを受ける際に一瞬で中へ切り込み1歩でシュートします。パスの出し手との連携力を高める方法もプログラムでは解説しています。
高低差でGKを手玉に取る!ハイジャンプのコツとは?
高低差を付けたシュートの決定率を上げるためには、ジャンプでできる限り高さを上げる必要があります。ジャンプのコツとして○を○○してしっかり踏み込み、○を引き上げることが上げられます。プログラムの高低差をつけたノーマークシュート練習の部分で解説しています。高さを自分の武器にしたい方必見です。
コースの確保に重きを置いた2歩切り替えしトレーニングとは?
パスを受けて1歩でシュート、3歩でDFを揺さぶるテクニックをある程度、身に付けたら、次に取り組むべきことはコースの確保です。DFをステップで揺さぶってもコースが狭くて打てない。そんな選手はシュート時の踏み込み足で○に跳んでる選手が多いです。プログラムでは2歩目で切り替えし、できるだけコースを作る足の使い方について説明します。
ステップの上級テクニック、ボール無しで移動してDFの虚をつくステップとは?
ハンドボールでは、ボールを受けてから3歩歩くことができますが、3歩目はDFもシュートコースのブロックを確実に意識してくるため、厳しい体勢でのシュートになりがちです。そのため、ボールを受けてからできるだけ少ない歩数でシュートに持っていく方法をお教えします。受けるまでのオフザボールの動きをプログラムを見て習得しましょう。
45度のシュートを確実に決めるために意識したい3つのポイントとは?
45度の選手はまず第一にもらう前にできるだけ○○○の位置を取っておくこと、第二にシュート時に○○○方向に向かって○○こと、第三に体幹を使って○へ流れないようにすることです。この3点を意識するだけで、シュートまでの技術確認とシュート成功率のUPにつながります。プログラムを見て励んでください。
ポジショニングとシュートを再確認するためのワイド練習法とは?
3人一組で行うワイドトレーニングを紹介します。センターの選手は、相手に悟られないようにシュートを狙い、パスを出します。パス出し後は次の動作を意識してバックステップを忘れずに行います。また45度の選手はワイドにとり、シュート時に3つほど注意していただきたいポイントがあります。プログラムで実演しながらこれらの注意点を中心に細説します。

得点率大幅アップできる、GKのリズムを崩すとっておきの方法とは?
○を使ったフェイントやスライドをうまく織り交ぜながら、GKのリズムを崩すシュートを放つための秘訣をプログラムで公開します。DFがいない状態で、外したくない、フリーの状態で絶対に決めることができるシュートを身につけたいという方に是非見ていただきたい内容です。
下川先生が練習で重視し続けた、シュートの7つの局面とは?
サイドシュートの運動経過を7つの局面に切り分けてそれぞれレクチャーします。これによりシュート動作の概要を理解し、上達を早めることができます。準備、受け、跳び込みなど、どれもシュートまでの過程に欠かせない要点です。プログラムを見てまずは頭で理解し、それを体得していきましょう。
上達スピードUP!サイドシュートの苦手な選手の欠点発見法とは?
サイドシュートの動作過程を、各局面に分けて説明します。どの局面も非常に重要な動作過程の一つですが、一つ一つ要点を押さえ体系的に把握していくことで、自分の欠点が見えてきます。プログラムではこれらの局面のどの部分が自分の欠点なのかや、悪癖を見つけ出し改善するためのトレーニングを紹介していきます。
得点力のある選手はこっそりやっている、相手GKの癖を見抜くコツとは?
ウォームアップ時でもやっている人はやっています。サイドシュートの決定率を上げるために、相手のGKの特徴や癖などを把握しておくことも大切です。試合前の準備のとしてはほかにもDFの守り方、アイコンタクトによるサイン、ボールの流れ等も重要になります。こういったことを意識することで、試合で高いパフォーマンスを発揮できる選手になることができるでしょう。
跳び込み時にラインを気にしてしまう選手にお勧めの矯正法とは?
練習の中で、ラインを確認する癖がついてしまっている選手がいます。ラインを見ずに感覚で跳びこめるよう、矯正していく必要があります。ラインを見てしまうことで、GKの動きを注視することができなくなり、決定力が下がります。プログラムを見て、日ごろの練習から無意識でラインを見てしまう癖を直していきましょう。
GKを硬直させる、有能なサイドプレイヤーがやっている跳び込みのコツとは?
サイドシュートにおいてズバリ、ジャンプの角度と高低差にその秘訣があります。GKの状況を受けの段階、または癖を早いうちに見抜き、7mライン方向に跳ぶか、0度に近い角度でゴールに向かって跳ぶかを判断します。そしてもう一つのポイントが、ジャンプの高低差。この2点をマスターしてGKより有利な状況でシュートを打てるようになる秘訣が、このプログラムの中にあります。
手首に秘訣が!GKが取りにくい軌道のシュートの投げ方とは?
最後のリリース局面で、手首の捻りで若干軌道をずらしてギリギリのところを狙う投げ方があります。もちろん、コントロールを最重要視しますが、そのためにまずボールの握り方について解説します。これを無意識にできるように訓練しながら、手首の返し方をお教えします。プログラムではこれらを総合的に解説しますので、手首の返しを利用したシュートが目に見えて上達していくでしょう。

体勢を崩さなずに左サイドからの跳び込みが上手い選手が知っているコツとは?
○脚で跳び込み、あえてDFに肩を当てに行きます。跳び込みでバランスを崩してしまうと、シュートの決定率は下がりますよね。上体を自分のイメージ通り保つことができれば、踏み込みでの苦手意識も少なくなるかと思います。プログラムを見て、左サイドのポイントゲッターになりましょう!
バウンドシュートが跳ねてしまう選手にお勧めの改善法とは?
バウンドさせようと意識しすぎてませんか?バウンドシュートは叩きつけるのではなく、手をサイドから○○に返して、流していく感覚で放ちます。手首のスナップ、言い換えると、手首の捻りと自分の腕の長さを鑑みて、各人に合ったリリースポイントになるよう調整し、体得しましょう。腕が長すぎる選手はたたむ、腕が短い選手は跳び込みでGKをずらすなど、即実践可能なテクニックをプログラムで手に入れることができます。
ループシュートが得意な選手と苦手な選手とにある小さな差とは?
わずかな肩の使い方で、GKを少し下にずらすことが可能です。これはスピンをかけたシュートでも利用できる技術です。インサイド下を狙う投げ方で跳び込み、その際にGKの動きをしっかり確認します。さらに自分の腕の長さを考慮して、タイミングをずらしながら弧を描くようにリリースします。言葉では分かりにくいですが、実演を交えたプログラムの解説を理解し実践することで、ループシュートが苦手な選手を、ループシュートでゴールを量産する選手へ上達させることも可能になります。
知らなきゃ大損、自分のリリースポイントを知る!とっておきの方法とは?
立体シュートと呼ばれる、ゴールに対して0度の位置から、腕だけを使って投げる練習法を紹介します。この練習で非常に重要なポイントは、身体を乗り出さないこと。自分のリリースポイントを感覚的に把握することができれば、サイドシュートの成功率は自ずと上がっていきます。また、この練習を応用したシュート練習も説明します。プログラムを見て、自分のリリースポイントを無意識に感じ取ることができるよう励みましょう。
シュートの感覚をつかみながら、ぶれない軸を作る方法とは?
体幹トレーニングを兼ねたシュート練習を紹介します。シュートの感覚については、自分の腕の長さを知ること、手首の捻りを使うこと。それを座った状態で行います。腹斜筋でバランスを取りながら、自分のリリースポイントを再確認していくことで、実戦での厳しい体勢からのシュートの決定率も上がります。プログラムを見て取り組むことで、ハンドボールに必要な状態動作と筋力がついてきます。
GKを出し抜く!歩数は少なく歩幅は大きくする理由と方法とは?
GKに準備をさせないこと。これに尽きます。つまり受けてから0歩または1歩でシュートに行くことで、シューター優位の体勢で打つことができ、隙が生まれやすくなります。歩数を少なくすることは受けについての解説で、歩幅と軸足については、角からの跳び込みについての部分でそれぞれ細説します。
積極的なDFを手玉に取るシュートモーションの体得法とは?
9m付近からの跳び込みにおいて、DFをかわすためのテクニックの一つを紹介します。サイドからは、0度方向とセンター90度方向に入り込むパターンがありますが、0度方向に入り込む際に、DFをできる限りセンターに引き付けて受けた後切り替えし、自分の○○から潜り込むように体を当ててDFをかわしにかかります。ゴールに対して逃げないことがポイントです。さらにそのあと体勢を立て直し、GKを見なければいけません。非常に難しいテクニックですが、プログラムを見て習得することができれば、自分の自信と武器になるでしょう。

サイドシュートに繋がるオフザボールの極意とは?
守備から攻撃へ切り替わった後、自分がボールをもらう際の一連の流れ、走り方と受け方を図解します。DFの戻りのスピード、状況に応じて臨機応変にスムーズに行うことが重要です。ボールを見失わないよう常に受けられる体勢を取りながら、DFを外側に誘ったり、内側に誘って素早く外に回り込んで、理想のサイドシュートに持っていくのか。それを理解し訓練できる極意がプログラムに詰まっています。
速攻時に効果的な走り方とは?
このプログラムでの実践練習内でいろいろなパターンを解説します。DFがつめてきた場合やDFの戻りが早い場合の対処法、自分より前でパスを受けるための秘訣など、試合で相手DFが対応できない動きを習得しましょう。
いかがでしょうか?
実は、あまりに盛りだくさんの内容の為、全てを紹介できないのが非常に残念ですが、
あなたがもし、サイドシュートで壁にぶつかっていること、悩んでいることがあれば、
このプログラムの中に必ず、解決のための糸口が見つかるでしょう。
このプログラムで劇的アップ!サイドシュート成功率
このプログラムで下川先生が公開してくれた練習方法の数々は、
いろいろな場面でのサイドプレイヤーが体得しておくべき
技術の粋を集めたものです。
導入することで得られるサイドシュートにテクニックは、
他のチームのプレイヤーにとっては、有効なテクニックばかりです。
単に、情況に応じたシュートのコースや飛び込みの角度、
コースの技術に加え、
上から叩きつけると はね過ぎてしまうのを防ぐバウンド
手を内側に返して バウンドを抑えるテクニック
チェンジアップ、ループなど、さらに
スピンにおいてもインサイド、アウトサイドそれぞれのテクニック
を身につけることができます。
今パッと考え、思いついただけでもこれだけのメリットがあります。
もし、人は何かを会得しようとした場合、必ず最も効率の良い方法を探します。
そして効率の良さとシンプルさは必ず比例します。
正しい練習方法を繰り返し実践すれば、
必ず通常の練習方法よりも、早くそして確実に習得できるはずです。
いかがでしょうか?
練習の方法自体が正しくなければ、その行動や努力が思うような結果に結びつかず、
最悪の場合、間違った癖をつけてしまい、のちのち修正に一層の困難を極めてしまうなんてことにもなりかねません。
スポーツが何であれ、スキルがどんなものであれ、
まちがった癖は、矯正には時間がかかるものです。
そんな危険性は確かにあるのです。
強烈でバリエーションに富んだサイドシュートを打てる選手と、
どれだけ努力しても上達しない選手がいる理由は、
全てこうした、正しく効果的な練習の方法を説明する指導者に出会えるか
否か、その違いがあるからに他なりません。
「あなたには遠回りして、挫折して欲しくない」
そんな思いから『ハンドボール・サイドシュート上達革命』を
ここまで、あなたに紹介させて頂きました。
ハンドボールで、攻撃と得点という視点で、
試合での勝敗に最も影響を及ぼす可能性が高い、
サイドプレイヤーや両45度プレイヤーのポジションです。
そのサイドプレイヤーと左右両45度プレイヤーの選手の
シュート決定力が低いのは、チームにとっても大きな弱点です。
なによりも、最も競った勝敗を分けるような場面での
サイドシュートの力が無い、ということは、その選手にとっても
責任が果たせないという、辛い立場を強いられます・・
このハンドボール・サイドシュート上達革命が、
きっと、そうした選手、または指導者のお役に立てるでしょう。
>>> ハンドボール・サイドシュート上達革命【元・日本代表サイドプレイヤー下川監督 指導】
-
走塁ランナーコーチ上達革命 ~一塁・三塁ランナーコーチ技術と、試合を想定した走塁技術の上達法 ~
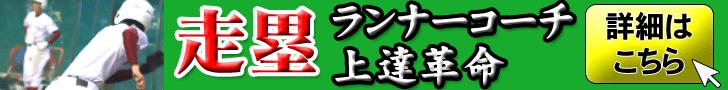
その中身の一部だけですが、紹介すると・・・
一塁コーチャーが絶対に習得すべき役割とは?
いかに○○○(少ない)カウントで○(先)の塁に行かすか。それを常に意識することです。一塁コーチャーの重要性について認識してない方がいますが、一塁コーチャーの的確な指示が、選手の不安を取り除く要因になり、1点に繋がることも多々あります。相手の守備位置や動きを常に観察しながら、バッターを動かす一塁コーチャーの役割を、このプログラムでフォーカスします。
一塁オーバーラン時のコーチャーの最重要な仕事とは?
自分も走者を引っ張っている感覚、それを感じさせる気迫が重要です。そのためには、コーチャーズボックスを目一杯使った指示をしましょう。さらに、オーバーランが本当に最善なのかを相手の守備位置等を鑑みて、常に考えましょう。
実はチーム力を左右している一塁コーチャーの脳力の差とは?
一塁コーチャーの役割を甘く見てる方多いと思います。ですが、そのコーチャーの判断一つで、単打がツーベースヒットになることもありますよね。一塁コーチャーはまさに縁の下の力持ちというべき、重要な立ち位置でもあるのです。ではうまくなるには?たとえば、試合前の外野のグラウンド状況を確認し、球の跳ね具合を把握する。相手チーム選手の守備力を念入りに調べるなどがあると思いますが、それらを含め、うまい一塁コーチャーになるためのちょっとした差について、しっかり解説していきます。
一塁走者に的確なリードをさせるコーチャーの役割とは?
一塁コーチャーは一塁走者のリードを確認し、最適な幅で取れるよう指示を送ります。ランナーは盗塁指示がでて、不安を持っていることもありますよね。スタートを切るのは走者ですが、それまでの構えはコーチャーも指示を送ることができます。選手の目線の高さで送ることがコツです。このプログラムを参考に実践してみてください。
二塁ランナーにとって重要な1塁コーチャーの役割とは?
一塁コーチャーの二塁ランナーへの指示は、一塁ランナーへの指示と比べて距離もあるので、複雑なものではなく、簡素な分かりやすい指示を送ることが重要です。そして、とりわけ欠かせないのが、コーチャーのポジショニング。二塁選手のリード幅の目安ともなるので、選手に合わせた立ち位置にしなければいけません。これらをまとめてこのプログラムで解説します。

こんな人に一塁コーチャーをやらせてはいけない・・・その特徴とは?
まず最低限、声が大きいこと。そして、ピッチャーなどの機微を察す洞察力に優れた選手。これは○○○○がうまかったり、相手のクセを見抜ける子などが向いています。このプログラムでもこの二つを備えた選手に実演してもらっています。ぜひ参考にしてみてください。
走者の黒子!理想の一塁コーチャーとは?
一塁コーチャーは、打者や一塁ランナーだけの指示、アドバイスを送ることだけが仕事ではありません。一塁走者へのアドバイスはもちろん、試合の流れの中での役割もあるし、相手チームの分析にも役割を果たすべきです。このプログラムを総合的に学んでいただければ、あるべきコーチャーの姿がきっと理解できるでしょう。
一塁コーチャーとは違う、三塁コーチャーの必須能力とは?
三塁コーチャーは、判断力と本塁へ極力回す勇気が必要です。一塁コーチャーと比べて、判断は難しいところが多く、経験を積むことが何より大事ですが、コツやテクニックでカバーできることも事実です。このプログラムでは三塁コーチャーの判断例について重点的に解説します。
二塁を回る走者に対する三塁コーチャーの最大の役割とは?
二塁を蹴る際に、見ては遅い場合があります。三塁コーチャーのゴーを確認してから二塁を蹴る必要があります。また、その際、三塁コーチャーの判断力が問われますが、目安となるタイミングについて、実演しながら説明します。このプログラムで学び、チームの機動力を引き上げましょう。
コーチャーが常に伝えるべき、ランナーに本塁を踏ませるために必要な意識とは?
セカンドランナーは常に本塁に戻るという意識を持つことが言うまでもなく重要です。これを全く考えていないと、本塁に戻れるタイミングでも、ストップしてしまったりすることがままあります。ぜひDVDを見て参考にしてください。
三塁を回る際にできるうまいコーチャーがやってるテクニックとは?
三塁側のボックスは、出てもいいルールなので、セカンドランナーが本塁に帰れそうな時は、三塁の近くに立ち壁になります。こうすることで、セカンドランナーが回る際に、無意識にふくらむのを防ぐことができ、無駄な距離を走る必要がなくなります。ただ回すだけではなく、そういったテクニックもDVDでは紹介します。

足が特別速くなくても二塁打を三塁打にすることができる判断ポイントとは?
例えば、右中間にいって、外野の間を抜ければ、大半はツーベースになりますよね。ですが、クッションボールでどれだけ外野が返球するのに時間がかかるかが分かれば、時に一気に三塁まで行くことも可能です。フェンスに当たればどれだけボールがはねるのか、球場の特徴等をコーチと共に把握し、判断するための材料にしていきましょう。
盗塁の指示が出たらやるべき、察知されないためのコーチャーの役割とは
盗塁のサインが出たら、ピッチャーの動作を見てから、スタートを切りますよね。問題はそのあとです。いいスタートが切れれば別ですが、アウトかセーフか微妙なスタートだと、走りが重要になります。その時に目線が○や○に行ってしまうと、減速の要因になってしまうので、注意します。また、盗塁スタートを切ったものの、打者が打った場合の対応についてもこのプログラムでは解説しています。
コーチャーが指導すべき、オーバーランでバランスを崩す選手の悪癖とは?
1塁を回るとき、体を内側に傾けますよね。しかしその際にバランスを崩して思わぬ怪我を招いてしまったことありませんか?そんな方に共通してみられる足の使い方があります。このプログラムを見て回り方を修正していきましょう。
コーチャーに学んでほしい、走塁が苦手な二塁走者へアドバイスすべき離塁の注意点とは?
およその目安となるものが、目の前にあります。離塁の位置取りは身長等を鑑みて自分に適した距離に構えるのが基本ですが、その目安となるのが1塁寄りに構えた1塁コーチのポジションです。アウトカウントによって多少の位置の調節が必要になりますが、それも全て網羅してこのプログラムでは解説しています。走塁に難のある選手や、苦手意識のある選手が、ぜひ参考にしてもらいたい方法です。
コーチャ―が指示すべき、戻りを意識しないシャッフルのコツとは?
帰塁を意識したシャッフルは、思い切ったスタートを切れなくする悪癖のひとつです。
理想的なシャッフルは、ややリードを短くとり、スタートを重視したポジションでシャッフルしていくこと。走塁についてあまり考えたことのない選手は目からうろこの内容かもしれません。このプログラムを見て、足が遅くてもテクニックでカバーする機動力のコツを習得しましょう。
ピッチャーがクイックで投げても効果的なシャッフルの秘訣とは?
ランナーなし時と同じオーバーではなくクイックで投げるピッチャーの場合、二塁ランナーは、特に意識すべきシャッフルの注意点があります。それは、目線を上下動させないことと、○○を意識しないことが巧いシャッフルをする秘訣です。

これだけは気を付けたい!シャッフル時の体重のかけ方とは?
シャッフルの目的は、できるだけ早く本塁に行くため。にもかかわらず戻る事を意識して左の方に体重が乗っている選手がちらほらおります。シャッフルは○○で踏み込み体重は右にかけます。このプログラムで映像とともに解説します。今すぐ修正可能な意識なのでぜひ参考に励んでください。
勝敗を分ける、三塁走者がやってしまうマズいスタートとは?
三塁ランナーの時のスタートの切り方が分からない、または自信がない選手に、ぜひ参考にして、植え付けていただきたいスタートの切り方があります。大きく分けてスタートの切り方は3つ。これらを意識できるかできないかで、試合ではかなり成功率の高いスタートが切れるようになります。
このプログラムで1つずつ明快に解説していきたいと思います。
ゴロゴーサイン時の的確な判断法とは?
ヘルメットの鍔とキャッチャーの構えた所の○に目線を置くことが重要です。そしてゴロゴーサインの時は、自分の目線に入ってきたらスタートを切ります。この位置に目線を置くことで、的確なスタートが切れるのに加え、フライの場合に瞬時に判断し戻る事が可能になります。言葉では分かりにくいですが、実演を見る事で正確に理解できると思います。
危険な走塁を生む!誤ったベースの踏み方とは?
1塁を駆け抜ける時は極力○足でベースを踏むようにします。これは1塁手との交錯を防ぐためです。また、ベースのどの部分を踏むかについても一挙に説明します。1塁以外のベースの踏み方についても別のチャプター内で取り上げています。このプログラムを見て塁ごとのベースランを体得しましょう。
セーフティーバントが決まらない・・・その理由とは?
低い姿勢で○○先を目標に駆け抜ける意識が大切です。この意識を植え付けるための練習法として、棒やトンボを用いたベースラントレーニングを紹介します。実演では悪い例も用意しました。このプログラムで正しい駆け抜け方を身につけてください。
打者走者がやってはいけない1塁でのオーバーランとは?
バランスを崩す選手、足をひねる方。まれにいますよね。その方に質問ですが、いつもどちらの足で1塁を踏んでいますか?おそらく左足だと思います。そしてベースの踏む箇所も、左前の角あたりかと思います。この2点をこのプログラムで改善し、怪我を減らしロスをしない走りを手に入れましょう。
「基本中の基本」なのにできていない選手が多い離塁時の注意点とは?
監督のサインを見る。内野外野の守備位置を見る。そして最も大事なのが相手バッテリーが準備をする前に素早く離塁することです。この3つの点を確認することが、ミスをしないために確認するべきポイントです。さらにこのプログラムでは、好走塁のために意識すべきテクニックをお教えします。
自分に合ったリード位置がわからず損をしている選手へのアドバイスとは!?
自分の身長+手を伸ばす+○○の位置に構えるのが目安です。そして実戦では、この歩数をピッチを見ずに頭で数えながら行う必要がありますこのプログラムを見て何度も繰り返し練習し、無意識に同じ位置で離塁できるよう体得しましょう。

帰塁で怪我をする選手の共通点とは?
1つ目は勢いをつけるために、右足の拇指球に力を入れて踏み込んでから跳ぶ意識。2つ目はベースに触れる時にけがをしないために○○を○に向ける。3つ目は一塁手のタッチまで少しでも長い時間を確保するためにベースの左側に触れるように意識すること。この3点を意識することが怪我なく帰塁するための気を付けるポイントです。
盗塁を成功させるために大切な、離塁の際の体の使い方とは?
盗塁時に意識するポイントは足裏、内腿、そして体のバランスです。○○○で踏ん張り太腿を○○へ向け、○対○の割合で踏ん張ります。これらはすべて、盗塁を念頭に置いた構えに不可欠なポイントです。盗塁の成功率を上げるための理想的な構え方を、このプログラムで体得しましょう。
スタートが命!盗塁時の上体動作のポイントとは?
盗塁がうまくなるための上体動作の秘訣はたった3つの動作を変える事。1つ目はお尻を少し持ち上げること。2つ目は目線は真下ではなく○○の○○○位先を見ること。三つ目は○腕で○を内側へ押すことです。これだけで、盗塁のスタートダッシュが見違えるほどよくなります。
エンドランを成功に導く走者の役割とは?
エンドランでは割り切った走塁が重要になります。スタートしてから○○位でバッターを確認し、打球がゴロなのかライナーなのか、フライなのか、状況で素早く判断します。ライナーの際は特に注意していただきたい点があります。このプログラムを参考に、チームの機動力強化に努めてください。
ブレーキにならないスライディングのコツとは!?
お尻で滑ってしまうと、勢いが失われてしまいます。ポイントは、塁を踏む方の足ではなく、その逆足と上体の使い方にあります。塁のできるだけ近いところから逆足を折り曲げて○で滑るような感覚で行います。その時上体を○○のほうへ少し倒すと、自然にこの形ができると思います。このプログラムではさらに踏み入ったところまで解説します。

微妙なシーンでセーフになるためのスライディングとは?
なぜ強いスライディングをする必要があるのか?それは微妙なタイミングでのタッチ時に、セカンドを威圧して手を引かせ、審判を惑わすためです。遠くからのろのろとスライディングするのではなく、できるだけ近くから減速せずに塁へスライディングします。いくつかのポイントがあるので、スライディングの秘訣についてこのプログラムで解説します。
技術で差が出る、二塁走者のリードパターンとは?
二塁走者は、アウトカウントによって、リードの位置を変えることがセオリーになっています。ワンアウトの時は二・三塁を結ぶ線上、ツーアウトは1歩後、スリーアウトはさらにもう1歩後ろに位置取ります。この理由と、それぞれのパターンでスタートを切る際の注意点について細説していきたいと思います。
ピッチャーのターンを考えた的確なリードの方法とは?
二塁走者は一塁走者と比較して、リードを大きくとれますよね。ですが、自分に合ったリード幅が分からないという選手を多々見かけます。アウトカウントも含め考慮し、自分に適したリードを手に入れましょう。このプログラムにはその方法を緻密に解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
上手いシャッフルとは?
シャッフルをスムーズに行うには、○○で蹴ることが重要です。シャッフル時に万一牽制されても、戻れるような動きかつ素早いシャッフルが理想です。そのキーポイントとなるのが、ズバリ○○で蹴り横に動くということです。非常に簡単に修正可能なポイントですので、このプログラムを参考にすぐ取り組んでみてください!

二塁ランナーのショートゴロへの対応とは?
二塁ランナー時に自分の正面に飛んでくるゴロの対応は、どうしていますか?
戻っていませんか?第2リードをとってから、ものすごく速いゴロでなければ、思いきってスタートを切ってもセーフになる可能性が高いです。このプログラムでは、実戦で失敗がないように、その感覚をつかむための練習を実演します。参考に取り組んでみてください。
これはトレーニングメニューに含まれているごく一部です。
もしかしたら、メニューの多さに驚かれているかも知れません。
しかし、安心してください。
練習場のいろいろな条件の下で、いろいろなシーンを想定し、
練習方法を説明していきますので、決して頭がパニックになることはありません。
実際の試合では、打球の飛び方、ゴロ、ライナーかフライか?
守備選手の守る位置や肩の力、
バッテリーの能力や癖などの条件が、練習でそのまま再現して対応を練習するなどということは、
100パーセント不可能です。
しかも、野球は通常屋外でやるものです。
グラウンドの条件によってのボールの転がり方、天候、とりわけ風の強さや
方向は、走塁の際にランナーにとっても、ランナーコーチにとっても
同じ条件下で練習を繰り返すことはできません。
このプログラムでの各トレーニングには、いろいろなシーンごとに
段階があり、習得すべき最も重要な基本がわかりやすく習得でき、
環境や状況が多少異なっても、十分応用できる練習方法を織り込みました。
その1つ1つがしっかりと結果が出るものですし、
試合に発生する状況への、「対応力」を身につけることが可能です。
どれをとっても大きな効果を実感できると思います。
野球に限らずスポーツは楽しむものですよね。
楽しい野球の技術の中でも、「走塁」はバッティング練習、守備練習と
合わせて実践できる側面もあるし、走塁のみでの個別トレーニングも可能です。
走ることが要求されるので、スタミナ的にも辛いものがあるかもしれません。
しかし、そうした練習を進める中であっても、
ただ辛い思いをしながら実践するより、試合でのいろいろなシナリオを
想定し、安全で、確実に、しかも楽に結果が出るほうがより楽しいですし上達も早い。
もしも・・・ ○○点差で負けて(勝って)いるとき、
自分が二塁走者でライト線に飛球が飛んだら・・・?
どんな本塁への進塁をしたらいいのか?
または、危険を避け、チャンスを広げるため、三塁で止まるべきか?
いろいろなシーンを想定した走塁テクニックとランナーコーチの
技術を習得する内容の一部を、既に一部写真付きで紹介しました。
練習しにくい走塁が、上達しないと悩んでいるより、グングン力が付いて楽しみに
変わったらどうでしょうか…?
>>> 走塁ランナーコーチ上達革命 ~一塁・三塁ランナーコーチ技術と、試合を想定した走塁技術の上達法 ~


